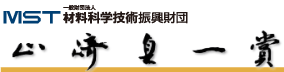第6回(平成18年度)山崎貞一賞 バイオサイエンス・バイオテクノロジー分野
新しい分子プローブの創製とそれを用いた興奮性神経伝達系の研究
| 受賞者 | ||
|---|---|---|
| 島本 啓子 (しまもと けいこ) | ||
| 略歴 | ||
| 1984年 | 3月 | 大阪大学理学部 化学科卒業 |
| 1986年 | 3月 | 大阪大学大学院 理学研究科有機化学専攻 博士前期過程終了 |
| 同年 | 4月 | (財)サントリー生物有機科学研究所 研究員 |
| 1991年 | 12月 | 大阪大学 博士(理学)学位取得 |
| 2001年 | 7月 | (財)サントリー生物有機科学研究所 主任研究員 |
| 2005年 | 4月 | 同 主席研究員 |
| 現在に至る | ||
授賞理由
我々の体を構成する細胞は種々の情報分子の受け渡しにより生命の恒常性を維持している。脳神経系の働きは、複雑な身体並びに精神活動を高度な情報ネットワークによって制御し、調和の取れた生命活動を維持する鍵を担っている。特にグルタミン酸はこの情報処理系において極めて大きな役割を果たしている。その働きを知るために様々な手法が用いられているが、島本啓子氏は細胞内で働く機能分子の阻害剤を確立する手法を用い成功した。これまでグルタミン酸がレセプターに働き、様々な機能を起こすことから、そのレセプターの解析に世界中がしのぎをけずってきた。これに対して島本氏はグルタミン酸を運ぶグルタミン酸トランスポーターに注目し、その遮断薬threo-β-benzyloxyaspartate(TBOA)の開発を行った。島本氏は基質分子の化学構造に輸送を遮断するような置換基を導入することで遮断薬(ブロッカー)型阻害剤に変換することを着想してTBOAの開発に成功した。(現在は、更なる化学修飾によってTBOAの活性を1000倍近く強力にすることにも成功し、より幅広い研究を可能にしつつある。)
島本氏が創出したTBOAはグルタミン酸トランスポーターを選択的に遮断し得る現在知られる唯一の薬物である。TBOAは1998年に発表されて以来トランスポーターを阻害した場合のグルタミン酸濃度変化やそれに伴う受容活動の解析、神経細胞死誘引条件の解明など、神経作用研究の新しい可能性を開いて、現在幅広く利用されている。TBOAでトランスポーターを阻害すると、速やかにグルタミン酸濃度が上昇すると共に、受容体の興奮の強度や持続時間が増大したり、小脳の長期抑制(LTD)が増強されたりする現象が観測される。この結果はトランスポーターが受容体の機能を制御していることを示しており、選択的な遮断薬なしには成し得なかった全く新しい研究である。一方、虚血条件下におけるグルタミン酸流出による神経細胞死や神経因性疼痛(アロデニア)はTBOAによって阻害された。これらの結果は、トランスポーターが疾患原因に関与することを証拠づけるとともに、その制御が新しい創薬ターゲットとなりうる可能性を示している。さらに、これまでは、グルタミン酸トランスポーターの役割はグルタミン酸が働いた後の不要物の除去にすぎないと考えられていたが、TBOAによって明らかにされた成果はグルタミン酸トランスポーターの役割が神経をグルタミン酸の神経毒性から守るとともに積極的に情報伝達の修飾を行っていることを示し、新しい概念を示したことになる。また、島本氏は、トランスポーター蛋白質を精製するためのアフィニティカラム作りや結晶解析用の重原子含有類縁体の合成も行い、この蛋白質分子の3次元構造機能の解明に道を拓いてきている。
島本氏が開発した薬物は、既に神経伝達に関する研究における標準的な物質としての地位を確立し世界中で使われている。当初は島本氏が自身で合成して求めに応じて世界の研究者に広く配布していたが、現在ではTBOA及び類縁化合物は広く市販され、国際的に情報伝達機構の解明に大きく貢献している。
研究開発の背景
グルタミン酸は哺乳動物の中枢神経系における代表的な興奮性神経伝達物質であり、記憶や学習といった高次の脳機能にも深く関与している。しかし高濃度のグルタミン酸が存在すると過剰な反応によって神経細胞の死が引き起こされるため、正常な状態ではシナプスにおけるグルタミン酸濃度は、主にグリア細胞に存在するグルタミン酸トランスポーターのはたらきによって厳密に制御されている。トランスポーターが脳の機能や神経疾患に与える影響を明らかにする研究には、その作用に選択的な阻害剤が必要である。しかし、これまでに知られていた阻害剤は競合基質として働き、グルタミン酸の取り込みは抑えるものの、代わりにその阻害剤自身が取り込まれてしまうために、それに伴うイオンの流れや細胞内外のグルタミン酸交換現象を止めることができなかった。このため、それらの阻害剤を用いた実験ではトランスポーターの機能を正確に観測することは原理的に困難であった。
業績内容
受賞者は基質分子の化学構造に輸送を遮断するような置換基を導入することによって遮断薬(ブロッカー)型阻害剤に変換することに成功した。このように見出された遮断薬 threo- - benzyloxyaspartate(TBOA)を用いることにより、トランスポーターの働きを抑えた状態で細胞外グルタミン酸濃度が正確に測定できるようになった。その結果、トランスポーターが機能することによって、神経細胞がグルタミン酸に起因する細胞死から免れているという機構が初めて明確に証明された。選択的な遮断薬TBOAが得られたことによりグルタミン酸トランスポーターの研究は飛躍的に進歩し、特にグリアが神経伝達に果たす役割が明らかになりつつある。TBOAは今や興奮性神経伝達を研究する上で不可欠の試薬である。さらに化学修飾によってTBOAの活性を1000倍近く強力にすることにも成功し、より幅広い研究を可能にした。光感受性保護基の導入や放射性標識化など、TBOAを基にして有機化学の手法で創出した分子プローブは、トランスポーターの機能解析や新規薬物検索に一層大きく貢献することが期待されている。また、この研究に先駆けて、グルタミン酸受容体リガンドの開発も行い、配座を固定したグルタミン酸誘導体を合成して、グルタミン酸が受容体に認識される際の活性配座を明らかにし、さらに複数のタイプと役割が知られている受容体のうちの特定のタイプに選択的に働く化合物を合成して精密な受容体研究を行った。
本業績の意義
グルタミン酸は神経伝達物質であると同時に神経毒として働くという二つの側面を持つ諸刃の剣であり、この分子による情報の伝達機構やこの分子の濃度を調節する機構を知ることは、記憶や学習という神経が関わる重要な生命現象の機構解明に繋がるとともに、神経疾患の病因解明や治療法開発にも寄与すると考えられる。グルタミン酸受容体を標的とした薬物はこれまでにも多く報告されてきたが、近年グリア細胞による神経制御が明らかになるに従い、主にグリアに存在するグルタミン酸トランスポーターの役割解明が重要となってきた。受賞者が創出したTBOAはグルタミン酸トランスポーターを選択的に遮断する。TBOAはトランスポーターを阻害した場合のグルタミン酸濃度変化やそれに伴う受容体活動の解析、神経細胞死誘引条件の解明などの神経作用研究の新しい可能性を開いて幅広く利用され、既に神経伝達に関する研究における標準的な物質としての地位を確立している。当初は自身で合成して求めに応じて世界の研究者に広く配布していたが、現在では市販もされている。化学を基礎として新たに分子プローブを創出する研究は、興奮性神経伝達機構のみならず、生命現象の解明に大きく貢献していくことが期待される。