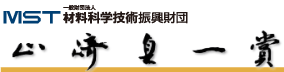最新の授賞
2025年9月22日(月)に開催した理事会にて今年度の受賞者を下記2分野2名に決定いたしました。
計測評価分野 授賞業績
題 目:X線位相イメージングの開発と応用
 |
||
| 受賞者 | ||
|---|---|---|
| 百生 敦(ももせ あつし) | ||
| 所 属 | ||
| 東北大学 多元物質科学研究所 教授 | ||
バイオ・医科学分野 授賞業績
題 目:革新的な診断・治療法の実装によるがんゲノム医療の拡大・推進
 |
||
| 受賞者 | ||
|---|---|---|
| 河野 隆志(こうの たかし) | ||
| 所 属 | ||
| 国立研究開発法人国立がん研究センター
がんゲノム情報管理センター センター長 |
||
受賞者記念コメント
計測評価分野
百生 敦様
受賞を知らされてのお気持ち、ご感想
卒論テーマを決める際、偶然にもX線回折に関する先進的な研究室に配属されることになり、それを契機にX線分野の研究を推進する研究者としての人生を歩むことになりました。本賞を受賞させていただくような業績を築くところまで至ることができ、感慨深く感じております。これまで多くの方々の協力を仰いできたこと、研究を進める上での様々な幸運に恵まれたこと、そしてこれまでの家族の支えに、心から感謝申し上げます。
研究開発の途中で苦労または工夫された点、エピソードなど
結晶干渉計を用いたX線位相イメージングの着想は、企業在籍時代に行ったシンクロトロン放射光利用研究と、学生時代の研究経験とが融合して生まれたものです。最初の数年間は、一人で自由に実験を重ねることが許され、今振り返れば少々無理のある働き方であったかもしれませんが、当時の環境が大きな糧となりました。一方で、真の実用化には実験室X線源を用いた手法へ発展させる必要があると痛感し、思い悩んだ時期もありました。転機は、皮肉にも大学に移ってから訪れ、結晶ではなく透過格子を用いる光学系の着想にたどり着いたことが、本賞につながりました。研究を進める上で、立ち位置を変え、視野を広げることの重要性を改めて実感しています。
受賞の対象となった研究の特筆すべきことや、一番アピールしたいこと
受賞対象となったX線位相イメージング手法は、Talbot干渉計と呼ばれる技術に基づいています。もともとは光学分野で開発されたややニッチな技術ですが、私はX線との相性が非常に良いと直感しました。課題は、使用する高アスペクト比X線格子の製作でしたが、これに無償でご協力くださった故・服部正教授(兵庫県立大学)に、まずはこの受賞を報告したいと思います。その後はプロジェクト化が進み、企業の参画も得て装置化が実現しました。「スーパーレントゲン」として報道いただいたこともあります。従来の影絵方式のX線撮影とは全く異なる技術を世に送り出せたことを、大きな誇りに感じております。
受賞の対象となった研究の、将来的な展望や期待について
吸収コントラストに頼る従来のX線撮影に比べ、X線位相イメージングには原理的に約千倍の感度が期待されます。しかし、特に実験室線源を用いた装置化においては、必ずしも原理通りの利得は得られていません。これまでに工業応用や学術応用を目的とした機器の一部実用化は進みましたが、医用機器としてはさらなる高感度化が求められています。その実現に向け、感度増幅を果たす光学設計やそのための格子製作技術に関連した研究にも着手しており、「第2世代X線位相イメージング」と呼べるような新たな展開を目指しています。
バイオ・医科学分野
河野 隆志様
受賞を知らされてのお気持ち、ご感想
30年以上にわたり行ってきたがんゲノムの研究の中での成果として、RET融合遺伝子という治療標的、NCCオンコパネルという遺伝子診断法の発見、開発や実装が評価されての受賞です。このような栄誉ある賞を頂いて、大変にうれしく、また、光栄に思います。この受賞は、これまでともに研究して下さった研究者、補助員、企業の方々、ご指導してくださった恩師、そして支えてくれた家族のおかげであり、大変に大きな感謝を感じています。ありがとうございました。
研究開発の途中で苦労または工夫された点、エピソードなど
長く進めてきた肺がんゲノム研究の過程で得られた共同研究者の総力を結集して、発見・実装できたのがRET遺伝子融合です。また、それを礎に、更なる共同研究者を得て、開発したのがNCCオンコパネルです。基礎的データの取得、検査法としての確立、規制対応など、様々な局面を、それぞれの場面で参画してくださる方々をrespectし、供に楽しみながらも苦労し協働で乗り越えることに、大きく尽力いたしました。
受賞の対象となった研究の特筆すべきことや、一番アピールしたいこと
自身の興味に基づいて進めていくのが基礎研究の醍醐味ですが、その中で、実装への契機が訪れることを、実践として学びました。それにきちんと向き合い、信頼を得ていくことで、次の契機につながります。その繰り返しが、最終的な実装への道筋となります。多くの研究者の方に、常に自分の成果を冷静に判断し、真摯に考え、地道にしぶとく向き合うことで、社会への実装ができることを、自分の受賞を通じて分かっていただきたく思います。
受賞の対象となった研究の、将来的な展望や期待について
がんの治療標的、診断法の実装は、世界中の基礎・臨床研究により「がんゲノム医療」として進歩しています。自分たちの発見もその一部を占めるものですが、がんゲノム医療の本質は決して派手でも魔法でもなく、日々の真摯な向き合いの総合体です。現在は、がんゲノム医療のデータをお預かりし、利活用するがんゲノム情報管理センターの長を務めさせていただいており、その活動を通じて、現在と未来のがんゲノム医療を支援・発展させたく思っています。